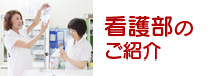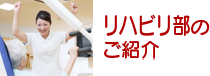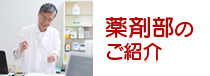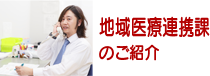看護部概要

当院は、2005年(平成17年)に新築移転した全室個室の慢性期病院です。
病室は、クッション材木を利用した広々とした個室になっています。
水橋駅前に立地し、広い駐車場も完備しているため、公共交通機関や自家用車での通勤が便利です。
現在、看護部は看護師・介護職員・歯科衛生士を含め、総勢約180名で日々の業務を行っています。
患者様へより良いサービスを行うため、各職員が協力して質の向上を目指し、日々の看護実践に取り組んでいます。
当院は年間休日が123日と多く、有給取得率も高いことから、職員がプライベートと仕事をバランスよくとれるよう努めています。
また、病院全体で「残業ゼロで働きやすい職場づくり」を目標に掲げ、残業を最小限に抑える取り組みを進めており、無理なく働ける職場環境を提供しています。
加えて、「あらゆるハラスメントは許さない職場づくり」も目標に掲げ、ハラスメントのない職場環境づくりを推進しており、職員が安心して働けるよう毅然とした対応をしています。
なお、当院には趣味のウィンタースポーツを楽しむために夏期シーズンのみ勤務する看護師もいますし、特定看護師(PICCの挿入など)・認定看護師・専門看護師・診療看護師(Nurse Practitioner:NP)の方々も受け入れ可能で、多様な働き方もできます。更新の際に自己研鑽として学会および研究会への参加や発表、教育研修の担当や指導といった実績・業績が必要になりますが、当院ではその点も含めて病院全体でサポートしています。
看護部理念
地域の皆さまのしあわせを願い真心をこめたケアを提供します
看護部方針
1.安全管理体制の充実を図り、事故防止・感染防止に努めます
2.専門的な知識・技術を習得し、質の高いケアを実践します
3.患者・利用者とその家族の満足度向上に努めます
4.医療従事者としてふさわしい言葉遣い・態度で対応し、患者・利用者はもとより地域の方々からも敬愛されるケアに努めます
ご挨拶

このたび、医療法人社団尽誠会 野村病院 看護部長に就任いたしました近村 厚子でございます。
これまで当院は、地域の皆様に支えられながら、慢性期医療を中心とした医療提供に取り組んでまいりました。
私はこれまで看護師として、また認定看護師・特定看護師として患者様一人ひとりの人生に寄り添うケアを大切にしてまいりました。
今後は看護部長として、看護部の仲間と共に、地域の皆様の安心としあわせのために、より質の高い看護を提供できるよう努めてまいります。
少子高齢社会の進展に伴い、医療の在り方も「病院完結型」から「地域完結型」へと大きく転換しています。
当院では、他医療機関や在宅医療との連携を重視し、慢性期以降の患者様の生活を支える看護の実践を通じて、地域全体の医療・福祉の質の向上に貢献していきたいと考えております。また、働く職員がやりがいを持ち、自分らしく成長できる職場づくりも重要だと考えております。チーム医療の一員としての責任と誇りを持ちながら、患者様・ご家族、そして地域の皆様に信頼される看護部を目指して、全力を尽くしてまいります。
今後とも、皆様のご指導とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
なお、看護部では看護学生、中途採用希望の看護師、介護職員の見学を随時受け付けております。見学希望の方は、ご遠慮なく看護部までお申し込みください。
看護部長 近村 厚子
看護部教育体制
看護部では、病院と看護部の理念に則した人材の育成を目指します。
教育理念
・当院の目指す医療を実践していくために必要な「ニーズをとらえる力」 「ケアする力」 「協働する力」 「意思決定を支える力」、4つの能力を備えた人材を育成していくと共に、個人が主体的にキャリア開発できる教育と支援を行う。
・社会人基礎力の「前に踏み出す力」 「考え抜く力」 「チームで働く力」の3つの力を基盤とした人間味あふれる人材を育成する。
教育目標
・病院理念と教育理念に則した能力向上のため、自らが主体的にキャリア形成することができる。
教育の実際
・毎月勤務時間内に約30分で研修を実施
・同研修を2~3回実施、あるいはビデオ研修
・レクチャーやワークショップ・体験型の研修を実施
・体験型では、シミュレーション教育による研修を実施(窒息時のケア、認知症状患者のケアなど)
・夜勤勤務前研修(シャドウとペアリングの2回実施)
・ポートフォリオ(「サクセス」)で目標管理の実施 など
ケアの実際
・末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)患者の管理
・摂食嚥下サポートチーム(SST:Swallowing Support Team) による嚥下評価と嚥下リハビリの実施
・人工呼吸器装着患者の管理
・アロマオイルによるハンドマッサージの実施
・ノーリフティングケア宣言 など
認定看護師・診療看護師の活躍について
当院は「私たちは、富山県内の患者・利用者、医療従事者から信頼され、選ばれる慢性期病院になります」というVisionを掲げています。
看護部でもVisionの実現に向けて、看護ケアの質の向上と熟練した看護技術を活かした実践を行い、日々のケアを向上させています。また、定期的な研修や技術向上の取り組みを通じて、看護師が専門性を活かし、チーム内で協力しながら質の高い看護を提供しています。
患者・利用者の尊厳を守り豊かな時間を過ごすために、Team Nurseは動きます。
認定看護師や診療看護師(特定行為修了者)をはじめ、看護師全員が技術や知識を持って、お互いが信頼できる活動を目指しています。
当院では、摂食嚥下障害を有する患者に対して医師、歯科医師、摂食嚥下障害看護認定看護師及び専任看護師、言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、管理栄養士が多職種で連携し、摂食嚥下状態の改善や誤嚥性肺炎の院内発症予防・低下を目標にして摂食嚥下サポートチームが活動しています。
摂食嚥下サポートチームは金沢医科大学病院 摂食・嚥下センターと連携し、摂食機能療法を行っております。また対象者には摂食嚥下機能回復体制加算2を算定し、摂食嚥下機能の向上を目指しています。
毎週の摂食嚥下カンファレンス及び隔週のVEカンファレンス(嚥下内視鏡カンファレンス)での診断と治療のディスカッション等に基づいて、摂食嚥下サポートチームは日々の活動をしております。
当院では、排尿の自立も患者様の尊厳を守る点からも非常に重要と考えております。このため、一般社団法人日本専門医機構認定 泌尿器科専門医である木村 夏雄医師(前 国保旭中央病院 泌尿器科主任医員)の指導のもと、排尿自立支援チームを2023年4月に立ち上げ活動を開始しました。現在は、医師、皮膚・排泄ケア認定看護師及び専任看護師、理学療法士、薬剤師が多職種で連携し、排尿自立を目標にして活動を行っています。
また、超高齢社会が進行する我が国では、2025年には65歳以上の5人に1人は認知症となる時代、すなわち認知症約700万人時代へ突入します。
このため、2023年11月より魚津緑ヶ丘病院副院長 兼 にいかわ認知症疾患医療センター長で日本精神神経学会精神科専門医・指導医である紋川 明和医師の指導のもと、認知症ケアチーム活動を行っています。認知症ケアチームでは医師・専任看護師、専任介護士が多職種で連携し、より良い認知症ケアを目標にして活動しています。
このほか、褥瘡があると、痛みなどによりQOL(生活の質)の低下をきたすとともに、感染を引き起こすこともあります。
このため、褥瘡対策チームでは褥瘡予防や治療、再発しにくい療養環境を整えるために、医師、皮膚・排泄ケア認定看護師及び専任看護師、専任介護士、理学療法士、管理栄養士が多職種で連携し活動しています。
このように、当院では摂食嚥下障害看護認定看護師、認知症看護認定看護師、皮膚・排泄ケア認定看護師の方々等が活動できるフィールドがあります。ご興味のある方はぜひお問い合わせください。
認定看護師(Certified Nurse: CN)について
1) 認定看護師とはどのような資格なのか看護師として5年以上の実践経験を持ち、日本看護協会が定める600時間以上の認定看護師教育を修め、認定看護師認定審査に合格することで取得できる資格です。
審査合格後は認定看護師としての活動と自己研鑽の実績を積み、5年ごとに資格を更新します。
2)認定看護師はどんな活動をする看護師なのか
患者・家族によりよい看護を提供できるよう、認定看護分野ごとの専門性を発揮しながら認定看護師の3つの役割「実践・指導・相談」を果たしてまいります。
| 日本看護協会 認定看護師 摂食嚥下障害看護認定看護師 |
中田 陽平、設樂 栄幸 |
|---|---|
| 日本看護協会 認定看護師 皮膚・排泄ケア認定看護師 |
近村 厚子 |
診療看護師(Nurse Practitioner: NP)について
1) 診療看護師とはどのような資格なのか看護師として5年以上の実践経験を持ち、大学院修士課程での医学教育を修了し、日本NP教育大学院協議会が実施するNP資格認定試験に合格することで取得できる資格です。
診療看護師は、患者の QOL向上のために医師や多職種と連携・協働し、倫理的かつ科学的根拠に基づき一定レベルの診療を行うことができます。
審査合格後は、診療看護師の質の標準化を図るため、NP資格認定試験合格者に対し、5年ごとに資格を更新します。
日本NP教育大学院協議会は、 診療看護師(NP)、「日本NP教育大学院協議会が認めるNP教育課程を修了し、日本NP教育大学院協議会が実施するNP資格認定試験に合格した者で、患者のQOL 向上のために医師や多職種と連携・協働し、倫理的かつ科学的根拠に基づき一定レベルの診療を行うことができる看護師」の育成を推進しています。
2) 診療看護師はどんな活動をする看護師なのか
診療看護師(NP)の役割は、医師、薬剤師等の他職種と連携・協働を図り、一定レベルの診療を自律的に遂行し、患者の「症状マネジメント」を効果的、効率的、タイムリーに実施することにより患者のQOLの向上を図ることです。
日本のNPは医師の包括的指示の下で、あらかじめ定められた特定行為を行うことができます。特定行為とは、厚生労働省が定めた行為であり、気管カニューレ交換や末梢留置型中心静脈注射用カテーテル(PICC) の挿入などを含み、現在では21区分38項目の行為が特定行為として定められています。
また、日常診療の中で医師と協働し診察、診断、治療を一緒に行うことがきます。
医療施設や在宅医療の場で、個々の患者の症状に対応した「症状マネジメント」をタイムリーに実施していくことにより疾病の重症化等を防止し、患者のQOLの向上を図ることができます。
3)多田 朋子診療看護師(医療法人社団尽誠会 野村病院 理事長補佐)からのコメント
近年、高齢化に伴う慢性疾患患者の増加・在宅医療の推進といった背景もあり、併存疾患を持ち合わせながら生活する方が増加しています。
患者・利用者が豊かな時間を過ごすために看護の視点と医学的視点を合わせ、タイムリーに!スピーディに対応し、患者・利用者の笑顔が見えるような医療提供ができるよう努めてまいります。
| 日本NP教育大学院協議会 診療看護師 特定看護師 |
多田 朋子 |
|---|---|
特定看護師・看護師特定行為について
超高齢社会が進展し、加えて医療の高度化・複雑化が進む中で、質が高く安全な医療を提供するため、チーム医療の推進が必要です。医療資源が限られる中で、それぞれの医療従事者が高い専門性を発揮しつつ、互いに連携し、患者様の状態に応じた適切な医療を提供することが求められています。このため、看護師には、患者さんの状態を見極め、必要な医療サービスを適切なタイミングで届けるなど、速やかに対応する役割が期待されています。
特定看護師とは、特定行為をおこなうために必要な研修を修了した看護師を指します。
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う診療の補助行為であり、厚生労働省が定める21区分38行為となっています。
特定行為研修とは、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能の向上を図るための研修であって、特定行為区分ごとに特定行為研修の基準に適合するものと定義されています。
特定行為研修修了看護師が、医師の指示のもとで一部の診療補助行為を行うことで、チーム医療の中での対応が円滑に進むよう努めています。また、患者やご家族の立場に立ったわかりやすい説明ができ、「治療」と「生活」の両面からの支援の促進に貢献します。
| 特定看護師 | 近村 厚子 皮膚・排泄ケア認定看護師 |
|---|---|
| 特定行為区分 | 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 |
| 特定看護師 | 設樂 栄幸 摂食嚥下障害看護認定看護師 |
| 特定行為区分 | 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 |
| 特定看護師 | 多田 朋子 診療看護師 |
| 特定行為区分 | 呼吸器(気道確保に係るもの)関連
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 ろう孔管理関連 栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心静脈注射用カテーテル管理)関連 創傷管理関連 創部ドレーン管理関連 動脈血液ガス分析関連 透析管理関連 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 感染に係る薬剤投与関連 血糖コントロールに係る薬剤投与関連 術後疼痛管理関連 循環動態に係る薬剤投与関連 精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 皮膚損傷に係る薬剤投与関連 |
介護福祉士の活躍について ~介護ICT、ロボット、ニューデバイスを活用し介護業務の効率化と質の向上を目指す取り組みを進めています~
わが国は65歳以上の割合が21%を超えた超高齢社会となっており、富山医療圏の介護需要は2020年を100とすると、2025年に116まで増加しその後も高止まりになると予測されています。
一方で、富山医療圏の生産年齢人口とよばれる15~64歳の人口は、2020年の280,198人から2045年には213,979人まで減少することが予測されています。
1)未来志向の介護について
当法人では、「病院・施設はこうあるべき」や「病院・施設だったら仕方がない」といった固定観念から脱却して、新時代にふさわしい病院・施設づくりを目指し、地域社会に貢献できる医療・介護サービスの提供に取り組んでいます。
介護福祉士が働きやすい職場環境を提供するため、現場の声を反映した改善活動を進めています。また、介護ICT、ロボット技術、ニューデバイスを積極的に導入し、業務の効率化だけでなく、患者や利用者へのサービス向上にも繋がる取り組みを進めています。
2)とろみ自動調理サーバーについて ~栄養経営エキスパート 2021年(令和3年)3月・4月号掲載~
具体的には、2020年(令和2年)9月にとろみ自動調理サーバーを導入しました。とろみ付けの手間が省けたため、介護スタッフの負担軽減になりました。
また、導入したことで均一な濃度と味のとろみ茶が提供可能になりました。
3)ICT介護である見守り支援システム「眠りSCAN」について ~ヘルスケア情報誌 けあ・ふる 2022年(令和4年)秋号掲載~
2021年(令和3年)12月には「医療・介護のICT化」推進の一環として、ICT介護である見守り支援システム「眠りSCAN」を介護医療院全室(100室)へ導入しました。
導入後は、ICTデータを積極活用し多職種連携を行っています。
4)排尿予測支援機器「D free」について ~北日本新聞 2023年(令和5年)10月3日朝刊掲載~
2023年(令和5年)9月には、排尿予測支援機器「D free」を導入しました。
排尿の自立は人間の尊厳を守ることにつながるため、当法人では重視しています。
5)認知症コミュニケーションロボット「だいちゃん」について ~北日本新聞 2023年(令和5年)10月3日朝刊掲載~
同じく2023年(令和5年)9月には、認知症コミュニケーションロボット「だいちゃん」を導入しました。
2025年には65歳以上の5人に1人は認知症となる時代、すなわち認知症約700万人時代へ突入します。
当法人では、認知症に対応できるスタッフ教育と認知症コミュニケーションロボットのハイブリッド対応で、認知症患者の増加に対応し、医療・介護スタッフが一丸となって支援してまいります。
6)介護ICT・ロボット・ニューデバイス導入の真の目的について
付け加えると、当法人では、介護ICTやロボット技術、ニューデバイスの導入を目的とするのではなく、それらの技術を活用することでスタッフの負担を軽減し、患者や利用者に寄り添う時間を増やすことが目的です。
また、介護の質向上と現場改革に取り組むことで、地域と医療従事者に選ばれる病院・施設づくりを進めており、そのための努力を続けています。
介護医療院 尽誠会
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/16/index.php?action_kouhyou_detail_034_kani=true&JigyosyoCd=16B0100071-00&ServiceCd=550
働きやすい職場環境づくり
職場でハラスメントが発生すると、職員の働く意欲が低下し能力が十分に発揮できないだけでなく、心身の不調をきたしたり職場環境が悪化するなど大きな問題になります。
当院ではハラスメント相談窓口はもちろん、コンプライアンス違反通報窓口も設置しています。
皆さんが働きやすい職場をつくるため、パワハラ(パワーハラスメント)、セクハラ(セクシャルハラスメント)、モラハラ(モラルハラスメント)等のあらゆるハラスメントは許しません。
男女共同参画社会について ~男女共同参画社会を積極的に推進する医療機関として~
男女共同参画社会とは、男性と女性がお互いを尊重し合い、職場、学校、家庭、地域などの社会のあらゆる分野で、性別にかかわらず個性と能力を十分に発揮し、喜びや責任を分かち合うことができる社会を指します。男女共同参画社会基本法では、男女共同参画社会を実現するための5つの柱を掲げています。
①男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性もひとりの人間として能力を発揮できる機会を確保する必要があります。
②社会における制度又は慣行についての配慮
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行の在り方を考える必要があります。
③政策等の立案及び決定への共同参画
男女が社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する必要があります。
④家庭生活における活動と他の活動の両立
男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動等ができるようにする必要があります。
⑤国際的協調
男女共同参画づくりのために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む必要があります。
男性も女性も、意欲に応じてあらゆる分野で活躍できるようになる男女共同参画社会が実現すると、職場には活気が生まれ、家庭生活は充実し、地域力も向上することが期待されます
働きやすい職場環境
・多様な働き方の実現により、男性も女性も能力を十分に発揮し、活躍できます。
・女性が政策や方針の決定に参加することで、新しい視点での提案・実施が可能となり、社会が活性化します。
充実した家庭生活
・家族みんながお互いを思いやりながら協力することで、心豊かな暮らしが実現します。
・男女が共に子育てや介護に参加することで家庭生活が充実し、その経験などを社会の様々な場面で活かすことができます。
活気あふれる地域社会
・男女が共に地域活動に参加することで、街に活気があふれ地域振興に繋がります。
・子どもたちが伸び伸びと育ち、誰もが安心して暮らせる環境が実現します。
野村病院グループでは、富山県知事政策局 働き方改革・女性活躍推進室長より男女共同参画チーフ・オフィサー(CGEO)に任命された青木 潤事務部長を中心に、今後も男女共同参画がさらに進むよう取り組みを推進してまいります。
「とやま女性活躍企業」について ~女性活躍を積極的に推進する医療機関として~
「とやま女性活躍企業」とは、企業の成長とウェルビーイング(真の幸せ)の実現に向けて、女性が活躍する県内企業等を富山県が認定する制度です。
認定には下記(1)から(7)の基準を満たす必要があります。
(1)女性活躍推進法で定める一般事業主行動計画を策定・届出、公表していること
(2)女性の活躍推進に向けた取り組みを行っており、下記基準を全て満たしていること
①女性の管理職比率が直近事業年度において全国の産業別平均値以上
②法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、各月ごとに全て45時間未満
③企業において女性活躍のための具体的な取り組みを行っていること
(3)決算額が直近3事業年度のうち1事業年度以上黒字になっていること
(4)男女共同参画チーフ・オフィサーを設置していること
(5)重大な労働関係法規に違反していないこと
(6)暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと
(7)県の研修を受講した社会保険労務士等による確認を受けていること
医療法人社団尽誠会 野村病院は「とやま女性活躍企業」として、今後も女性が活躍しやすい職場づくりを積極的に推進してまいります。
ダイバーシティ・エクイティとインクルージョン DE&I(DEI)推進について ~ダイバーシティ・エクイティとインクルージョン DE&I(DEI)を積極的に推進する医療機関として~
医療法人社団尽誠会 野村病院の「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン DE&I(DEI)」推進宣言
医療法人社団尽誠会 野村病院では病院理念として、ミッション Mission(果たすべき使命・役割)「私たちは、富山県内の医療・介護ニーズに応え、慢性期以降の患者・利用者の人生を支えます」、ビジョン Vision(目指す姿)「私たちは、富山県内の患者・利用者、医療従事者から信頼され、選ばれる慢性期病院になります」、バリュー Value(行動指針・価値観)「私たちは、医療従事者同士のチームワークを大切にして、患者・利用者の立場に立った医療・介護サービスを提供します」を掲げております。
このバリューの体現が、当院のビジョン、ミッションの体現につながると考えております。
医療法人社団尽誠会 野村病院では、多職種連携によるチーム医療を推進しております。
この多職種チームを構成する際に、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン DE&I(DEI)を重視しております。
特に女性が働きやすい職場づくりを推進しておりますが、本来は女性や男性といったジェンダーを問わず誰もが働きやすい職場づくりが必要と考えております。
すなわち、男女共同参画推進の先にはダイバーシティ(多様性)推進があると考えております。
医療・介護を取り巻く環境は加速度的に日々刻々と変化しています。
その変化に対応するために、医療法人社団尽誠会 野村病院ではダイバーシティ(多様性)の視点を重視しております。多様な人材によって構成された医療・介護施設であれば、日々刻々と変化する医療・介護を取り巻く環境に対し、適切に対応することが可能と考えます。
また、多様な人が働く医療・介護施設の中で、それぞれのスタッフに合った対応をすること、すなわちエクイティ(公平性)も重視しております。
すなわち、医療法人社団尽誠会 野村病院ではダイバーシティ(多様性)を認めるのはもちろんですが、その上でエクイティ(公平性)の考え方を取り入れながらダイバーシティ(多様性)を受け入れております。
加えて、多様なスタッフが能力を発揮できるようにすること、すなわちインクルージョン(包摂性)も推進しています。
これにより、病院風土をさらに良い方向に変えていきたいと考えております。
医療法人社団尽誠会 野村病院では、従来取り組んできた「ダイバーシティ&インクルージョン」にエクイティの考えもプラスした概念、「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン DE&I(DEI)」を推進し、多様なスタッフが輝き、そして活躍できるような職場環境づくりを目指しています。
医療法人社団尽誠会 野村病院 理事長 野村 祐介
1)女性の活躍推進について
●管理職に占める女性の割合を引き続き50%以上を目標に取り組んでいます
・新人事制度の導入し、女性がキャリアアップできる環境を整備し、管理職候補の把握と育成に努めております。
●妊娠・出産・子育てしやすい職場環境や制度を整えています
・パパ育休制度の推進し、パパ育休制度により女性側に偏りがちな育児や家事の負担を夫婦で共有することで、仕事と生活が両立しワークライフバランスのとれた働き方を推進しています。今後も、イクメンスタッフが働きながら安心して子育てができる環境づくりを進めてまいります。
・女性の育児休暇取得率は100%、サポート体制が整っているため、引き続き育児休暇などのブランクからも復帰しやすい環境です。
・とやま育児休業取得促進補助金を活用し、育児休暇取得者に対して経済的支援を実行、法個人一体で取組む姿勢を取得該当職員に明示しています
・イクメン宣言及びイクボス宣言を実施、イクボス企業同盟とやまに加入、とやま女性活躍企業の認定を受け、内外ともに広く取組みを発信しています
●女性目線の企画発案を実現しています
・女性に人気のある一部の人気店の移動販売や、ワッフル等の軽食販売キッチンカーの招聘を実現、「他にはない非日常感のある職場」づくりに注力しています。
2)高齢者の活躍推進について
●新人事制度を導入しています
・定年を65歳に延長、かつ70歳までの雇用延長制度を導入済みです
・若手から高齢者まで実力に見合う業務開発に取組みます
3)障害者の活躍推進について
●何らかの障害があっても活躍できる環境を整備しています
・新規入職スタッフに対しては、必要に応じて設備導入や対応アプリにてできる限り支援しています。
4)多様な働き方制度の整備について
●季節限定勤務の看護師を採用しています
・趣味のウィンタースポーツを楽しむために夏期シーズンのみ勤務する看護師がいます
●子育て世代に都合のいい勤務時間を整備しています
・病棟勤務の看護師は9時始業としており、子供を預けてから出勤できます
・子育て世代に都合のいい勤務時間帯で、残業なく早退の必要性が少ない就業時間の設定をしています
●介護と仕事を両立できる制度づくりをしています
・介護休暇は複数のスタッフが過去に取得しています。
・家庭環境を熟知した所属部門長が、個々の生活環境に添った無理をさせないシフト勤務や休暇を配慮しています
●ウェルビーイング経営を実践しています
・ウェルビーイング経営の実践により、各職種で推進しているタスクシフトも「働き方」を抜本的に見直しする事で、働きやすい職場環境を目指した取組みの一環です
5)ワークライフバランスの重視について
●残業ゼロ運動を推進しています
・病院全体で『残業ゼロで働きやすい職場づくり』を推進しています
・当院の時間外労働平均は約2.0分/月でほとんどありません、今後も残業ゼロで働きやすい職場環境づくりを進めてまいります。
●有給休暇取得を促進し取得率を前年度より5%向上を目標にしています
・当院の有給休暇取得率は90%であり、90%以上の実績キープを目標としています。引き続き、有給休暇を取得しやすい環境づくりの整備と有給休暇の制度の周知や情報提供を行っています
・有給休暇を取得していない職員に声がけ等を行い、取得も促しています
6)スタッフの状況に合わせた職場環境の提供について
●エクイティの考え方を取り入れた各種取り組みを行っています
・フェムケア休暇を創設、妊娠・不妊分野の体調管理と治療をサポートしています(専用相談窓口を設置)
・事務部門担当者が、定期的に男女共同参画やフェムテック、アンコンシャス・バイアス等のセミナーに参加しスタンダードな取組を取得しています
・NFWG(Nomura Femtech Working
Group)を設置、随時開催により、新企画や福利厚生面アップに向けたブレーンストーミングを実施しています
・男性の育休所得率100%、管理部が取得斡旋し事務部人事担当者が制度面をレクチャーする体制を整えています
D&I AWARD 2024について ~D&I AWARD 2024において「ベストワークプレイス」に認定~
株式会社JobRainbowが主催する D&l AWARDは、2021年度より始まったダイバーシティ&インクルージョンに取り組む企業を認定する日本最大のアワードです。
日本で活動する応募企業のD&Iの取組みを独自の指標で採点し、スコアに応じて認定を授与します。
医療法人社団尽誠会 野村病院はD&I AWARD 2024において「ベストワークプレイス」に認定されました。
医療法人社団尽誠会 野村病院では、従来取り組んできた「ダイバーシティ&インクルージョン D&I」にエクイティの考えもプラスした概念である「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン DE&I(DEI)」を推進し、多様なスタッフが輝き、そして活躍できるような職場環境づくりを目指しています。
アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)について
医療法人社団尽誠会 野村病院では多様性を認めるのはもちろんですが、その上で多様性を受け入れてその能力が発揮できるようにすること、すなわちダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。
しかし、ダイバーシティ&インクルージョン推進を阻む一因として、アンコンシャス・バイアスがあげられます。
アンコンシャス・バイアスとは無意識の偏見であり、自分自身では気づいていない歪んだあるいは偏った見方や考え方のことをいいます。
例えば、「女性だから管理職は無理でしょう」とか「女性だから出産したら家事・育児に専念すべき」といった考えが該当します。また、介護医療院では介護ICTを進めていますが、「シニアスタッフはパソコンが使えないからパソコン業務は無理でしょう」ということもアンコンシャス・バイアスに該当します。
私たちは固定観念や先入観、思い込みを捨てて、アンコンシャス・バイアスの解消に取り組んでいます。
アンコンシャス・バイアスの解消により、ダイバーシティ&インクルージョンをさらに推進し、多様なスタッフが輝き、そして活躍できるような職場環境づくりを目指しています。
「イクメン企業宣言」「イクボス宣言」について ~男性の育児と仕事の両立を積極的に推進する医療機関として~
2022年10月より施行された「産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)」により、男女ともに育児と仕事の両立がしやすくなりました。
当院では、「富山県内の患者・利用者、医療従事者から信頼され、選ばれる慢性期病院」を目指し、働きやすい職場づくりを進めています。とりわけ、医療従事者がライフステージに応じて活躍できる環境整備の一環として、育児支援にも力を入れています。パパ育休制度の活用により、育児・家事の負担をパートナーと分かち合いながら、ワークライフバランスのとれた働き方が実現可能です。
当院では、厚生労働省の「イクメンプロジェクト」に賛同し、2023年4月には「イクメン企業宣言」および「イクボス宣言」を行いました。
男性職員の育児休業取得実績もあり、今後も、誰もが安心して子育てと仕事を両立できる職場環境づくりに取り組んでまいります。
共働き・共育て推進事業「共育(トモイク)プロジェクト」について ~男性育休の取得促進と男女の家事・育児分担の見直しを推進する医療機関として~
厚生労働省の「イクメンプロジェクト」は2025年から「共育(トモイク)プロジェクト」にリニューアルされました。
当院では「共育(トモイク)プロジェクト」に賛同し、引き続き男性育休の取得促進と男女の家事・育児分担の見直しに取り組んでまいります。
フェムテックで安心して働ける病院づくり ~女性特有の健康課題をテクノロジーで解決する~
スタッフの約80%が女性であり、「とやま女性活躍企業」として認定された当院は、女性特有の健康課題に対して病院全体で向き合っていく必要性があると考えております。
その方法のひとつとして、フェムテックの活用が期待されています。
フェムテックは、FemaleとTechnologyをかけ合わせた造語で、女性特有の健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスなどを指します。
女性特有の健康課題の一つとして月経があげられます。月経が不規則であるといつ月経になるか予測がしづらく、仕事中に突然月経がはじまってしまい、日中であればまだしも夜勤中だと生理用品の持ち合わせがなく困ってしまう可能性があります。
医療従事者から選ばれる病院になることをVisionとして掲げる当院では、安心して勤務できる働きやすい病院づくりのため飲料とあわせて女性用衛生用品(生理用ナプキン)が購入できる「女性ヘルスケア応援自動販売機」を、2024年(令和6年)2月に設置しました。
また女性用衛生用品(生理用ナプキン)の価格の約4割を法人が負担することで、福利厚生の充実による働きやすい病院づくりも目指しています。
ジェンダード・イノベーションとは ~ジェンダード・イノベーションの視点から女性活躍を推進する~
第6期科学技術・イノベーション基本計画において、ジェンダード・イノベーションとは科学や技術に性差の視点を取り込むことによって創出されるイノベーションと定義されています。
従来は男性を基準としていましたが、性差の観点を導入することで新たな視点を見出すことが従来との違いになります。
医療法人社団尽誠会 野村病院では、ジェンダード・イノベーションによる考えを様々な領域で取り入れております。
BCP(事業継続計画)対策の防災備蓄品に生理用品を用意することや、食事介助のスプーンを均一で用意するのではなく小さなスプーンも用意し女性・男性それぞれに適したスプーンを用意することなどは、ジェンダード・イノベーションによる考えが反映されているといえます。
医療法人社団尽誠会 野村病院は、今後も女性が活躍しやすい職場づくりを積極的に推進してまいります。
次の未来に向けてプラネタリーヘルスの視点を重視する ~次の50年に向けたアクション~
医療法人社団尽誠会 野村病院は2017年に開院50周年を迎え、看護部も次の50年に向けて動き始めました。
2021年10月には、SDGsに関する取り組みを「富山県SDGs宣言」として宣言しました。
プラネタリーヘルス、直訳すると地球の健康になりますが、地球環境と人間の健康が密接に関係している状態を指します。昨今、気候変動や生物多様性の喪失、環境汚染などが地球規模的な課題となっています。例えば、気候変動による健康への影響としては、近年の自然災害関連死や熱中症などがあげられます。
当院の病院庭園には多様な緑、すなわち植物があります。植物は光合成によって二酸化炭素を吸収するため、微力ながら温室効果ガスである二酸化炭素削減に貢献してきました。
2020年には、各階共用棟及び東病棟において一般照明をLED照明へ切り替えました。2021年から2022年にかけては、全病棟の空調設備を高効率空調設備へ更新しました。
これらの取り組みにより、病院全体として二酸化炭素排出量の削減に取り組んできました。
次の未来に向けて、看護部を含め病院全体でSDGsはもちろん、その先にあるプラネタリーヘルスの視点を重視しています。
「VUCA時代」における医療法人社団尽誠会 野村病院
現代社会は、「VUCA」と呼ばれる変化の時代に突入しています。
VUCAとは、以下の4つの言葉の頭文字を取ったものです。
• Volatility(変動性)
• Uncertainty(不確実性)
• Complexity(複雑性)
• Ambiguity(曖昧性)
これらは、将来の予測が極めて困難な状況を意味しています。医療・介護の分野も例外ではありません。
1)変動性(Volatility)への対応
新型コロナウイルス感染症の流行をきっかけに、医療現場ではオンライン学会や遠隔会議などが日常化しました。
“当たり前”が急速に変わる今、私たちは、時代の変化に敏感であり続け、必要なときに即断・即行できる組織であることが求められています。
2)不確実性(Uncertainty)への備え
自然災害や新興感染症など、先が読めない時代。
その中でも、過去の経験から学び、柔軟で持続可能な体制を整えることが、医療機関としての責務と考えています。
3)複雑性(Complexity)への視野
感染症や高齢化、介護問題など、複数の要素が絡み合う中では、単純な解決策が通用しません。
国内外の動向に目を向け、多角的な視点を持って意思決定する必要があります。
4)曖昧性(Ambiguity)への理解
かつてのように、正解が一つである時代ではなくなりました。
病院広告ひとつとっても、紙媒体からウェブ・SNS・動画へと手段が多様化しています。
私たちは、多様なニーズを受け止め、柔軟に適応できる感性と行動力を大切にしています。
VUCA時代を生き抜くために
医療法人社団尽誠会 野村病院では、こうした不確実な時代に対応するため、法人としてのビジョンを明確に掲げ、スタッフ一人ひとりと共有し、同じ方向を見て歩んでいます。
医療・介護を取り巻く環境が大きく変わり続ける今、私たちは「地域から、そして医療従事者から選ばれる病院」であり続けることを目指します。
入職者の声

2016年度(平成28年度) 入職者の声(女性看護師)
以前は急性期病院に勤務していました。慢性期病院は初めてでしたが、先輩看護師にいろいろと教えてもらいながら、知識と技術の向上を目標に日々頑張っています。
子育て中なので、育児をしていても働きやすい、定時に帰れるという2点が病院を選ぶポイントでした。
入職してみると、ほぼ定時に帰れますし、育児にも理解がある病院だったので、働きやすい環境で安心しました。
家庭と仕事の両立は大変ですが、同じ境遇のスタッフも多く、子育ての話などお互いに情報交換しながら楽しく働いています。
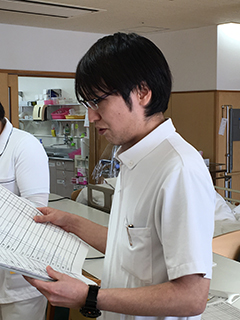
2018年度(平成30年度) 入職者の声(男性看護師)
人を助ける仕事がしたいと考え、看護師になりました。自己研鑽のため、急性期病院で忙しい日々を過ごし、それなりに充実していました。ただ、毎日忙しく、患者さんとのコミュニケーションが思うように取れず悩んでいました。
患者さんともっとコミュニケーションをとって、患者さんに寄り添った看護を実践していくためには、慢性期病院のほうが向いているのではないかと思い当院に入職しました。
当院は、若手からベテランまで幅広い年代の方々が働いています。
このため、わからない事や困ったことがあっても、誰かが対応してくれます。他職種で対応が必要な場合でも、先生方へ話をしにいけば相談に乗ってくれます。
職員間の距離が近いことは当院の魅力のひとつだと思います。

2013年度(平成25年度) 入職者の声(介護職員 女性)
私は、介護と全く違う職種から入職しました。当時は、働きながらもやりがいを今ひとつ見出せませんでした。
せっかく働くなら社会に貢献できる仕事をしようと思い、介護業界に入りました。
最初は介護の仕事についてほとんど知らないままの入職でしたが、周囲の方々に支えられ少しずつ関わる業務が増えていき、現在では充実した日々を過ごしています。
介護は人と関わる仕事なので、ありがとうと感謝の言葉をもらうととてもうれしく、今では仕事へのやりがいを感じています。

2018年度(平成30年度) 入職者の声(介護職員 男性)
将来は人の役に立つ仕事をしたいと考え、介護職につきました。
以前は他の医療機関で働いていましたが、見学へ行った際の雰囲気や院内の明るい感じが決め手となり、当院へ入職しました。
50年以上の歴史がある病院ですが、良い慣習は継承し、悪しき慣習は改善するという風土ができつつあるように思えます。
患者様、患者様家族にきて良かったと思っていただける病院づくりに、私も微力ながら取り組んでいきたいと思っています。
病棟のご紹介

- 2階東病棟

- 2階西病棟

- 3階東病棟

- 3階西病棟