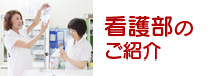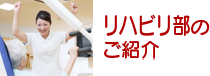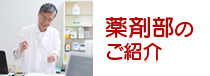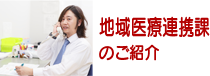内科外来案内
内科外来では、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病、循環器疾患、消化器疾患、呼吸器疾患などの幅広い診療を行っていますが、高齢者になると複数の疾患を抱えている人が多くなります。
超高齢社会を迎えた我が国では、複数の疾患を優先順位をつけて包括的に管理できる老年内科医の重要性が増しております。
当院は、その使命を担う立場にあると考えております。
また、大学病院や近隣の地域基幹病院とも連携して診療にあたっており、専門的な検査や治療を要する場合は速やかに高次医療機関への紹介を行っています。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 午前 8:30〜12:00 (受付は11:30まで) |
● | ● | ● | ● | ● |
| 午後 13:00〜17:00 (受付は16:30まで) |
● | ● | ● | ● |
● |
●:淵上映子医師(内科・老年内科)
外来診療医は、都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。
専門外来案内
野村 亮介医師 (消化器内科・肝臓内科)
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本肝臓学会認定肝臓専門医
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医
日本消化管学会認定胃腸科専門医
日本医師会認定産業医
野村 祐介医師 (循環器内科・消化器内科)
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医
日本老年医学会認定老年科専門医・指導医
日本心臓リハビリテーション学会認定心臓リハビリテーション指導士
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医
日本消化管学会認定胃腸科認定医・専門医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター
医学博士
| 専門外来 | 水 午後 |
|---|---|
| 担当医師 | 野村 祐介医師(日本循環器学会認定 循環器専門医、日本消化器病学会認定 消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医、日本老年医学会認定 老年科専門医・指導医、日本内科学会認定 総合内科専門医) ほか |
PICC外来案内
栄養状態が低下している方や、1週間以上にわたりお食事をお口から摂ることが難しい方には、中心静脈栄養という方法で、点滴から栄養を補うことがあります。この点滴は高カロリー輸液とも呼ばれ、高濃度の成分を含んでいます。そのため、手や腕の血管(末梢静脈)から投与すると、血管への刺激により痛みや炎症を引き起こすことがあるため、中心静脈(上大静脈や下大静脈)にカテーテルと呼ばれる細い管を挿入する方法が必要となります。
従来は、首や鎖骨の下あたりにある太い静脈からカテーテルを挿入する方法がよく用いられてきました。この方法では、動脈を誤って刺してしまう(動脈誤穿刺)、肺に穴が空いて肺から空気が漏れる(気胸)、あるいは肺が傷ついて肺が収納されている空間である胸腔内に血液が溜まる(血胸)といった合併症が報告されています。これらのリスクに配慮し、より安全な選択肢として、近年は別の挿入方法も検討されるようになりました。
2017年3月に発表された、一般社団法人 日本医療安全調査機構 医療事故調査・支援センターの報告では、末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)による代替を含め慎重に決定するよう提言がありました。PICCとは、腕の静脈から挿入し、中心静脈に先端を留置するカテーテルのことです。従来の挿入方法と比べて、合併症や感染のリスクが少ない可能性があるとされています。
当院では、2017年5月より、このPICCを用いた中心静脈栄養の管理を導入しております。挿入の際は、すべての患者様に対し、オラネキシジングルコン酸塩(オラネジン®)による皮膚の消毒とマキシマルバリアプリコーション(高度無菌遮断予防策)の徹底による感染予防策を実施しています。
これらの取り組みにより、感染予防と医療安全の向上に努めております。
■当院におけるPICCの特徴
1.安全性を重視しX線透視下でPICCを挿入しています
2.安全性を重視し穿刺用超音波を用いてPICCを挿入しています
3.皮膚消毒薬にオラネキシジンを使用しPICCを挿入しています
外来においても施行しておりますので、適応患者様がいらっしゃいましたらご相談ください。
| PICC外来 | 月~金 午後 |
|---|---|
| 担当医師 | 野村 祐介医師(日本循環器学会認定 循環器専門医、日本消化器病学会認定 消化器病専門医、日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医、日本老年医学会認定 老年科専門医・指導医、日本内科学会認定 総合内科専門医) ほか |
オンライン診療の基本方針
当院では、患者さんのより良い医療の実現のため、オンライン診療を積極的に推進しています。
オンライン診療は、患者さんの日常生活の情報も得ながら医療の質を向上させ、必要な患者さんへの医療アクセスを確保し、治療への積極的な参加を促すことで、治療効果を最大限に高めることを目的としています。この基本理念は、医療法第一条に定める「医療を受ける方の利益の保護と良質かつ適切な医療の効率的な提供を通じて、国民の健康維持に貢献すること」に資するものです。
医師と患者さんには、以下の点をご理解いただいた上で、オンライン診療を受けていただくことを推奨します。
医師-患者さんの信頼関係と守秘義務
オンライン診療は、医師と患者さんの相互の信頼関係に基づいて行われます。そのため、普段から対面診療で関係性を築いている医師が担当することを基本とし、対面診療と適切に組み合わせることを心掛けています。
医師の責任
オンライン診療における医師の診療行為の責任は、原則として担当医師が負います。医師は、オンライン診療で得られる情報が十分であるか、それに基づいて適切な診断ができるかを慎重に判断します。
もしオンライン診療が適切でないと判断された場合は、速やかに診療を中断し、対面診療に切り替えることがあります。また、患者さんの医療情報の漏洩や改ざんがないよう、情報管理とセキュリティ対策を適切に行います。
医療の質と患者さんの安全確保
オンライン診療においても、安全で最善の診療が行われるよう、対面診療と同様に治療効果の評価を定期的に行います。万が一、患者さんの急変など緊急時には、速やかに対応できるよう体制を確保しています。
オンライン診療の限界と正確な情報提供
オンライン診療では、対面診療と比べて得られる患者さんの心身の状態に関する情報が限定される場合があります。医師は、こうしたオンライン診療の特性や限界を事前に患者さんやご家族に詳しく説明し、利点や起こりうる不利益について十分に理解していただいた上で診療を行います。
安全性・有効性のエビデンスに基づいた医療
当院のオンライン診療は、医学的な安全性、必要性、有効性のエビデンス(科学的根拠)に基づき行われます。特に、対面診療と比べて得られる情報が少なくなることを考慮し、各種学会のガイドライン等に沿って適切な診療を実施します。治験や臨床試験等を経て安全性が確立されていない医療を提供することはありません。
患者さんのご希望に基づく提供
オンライン診療は、その利点と起こりうる不利益を患者さんがご理解いただいた上で、「受けたい」とご希望された場合に実施されます。研究目的や医師側の都合のみでオンライン診療を行うことはありません。
当院で施行可能な検査
- 嚥下内視鏡検査
- X線単純撮影(胸部X線、腹部X線、骨部X線 等)
- CT検査(頭部CT、胸部CT、腹部CT 等)
- 消化管X線造影(嚥下運動評価、食道蠕動運動評価、注腸造影 等)
- 心電図検査、ホルター心電図
- 血液検査(血液一般、電解質、肝機能、腎機能、蛋白、脂質、糖尿病、炎症反応、凝固、内分泌、アレルギー、感染症、腫瘍マーカー 等)
- 血液ガス分析検査(動脈血ガス分析、静脈血ガス分析)
- 尿検査(尿比重・尿中蛋白・尿糖・尿潜血・尿沈渣 等)
- 便潜血検査
- 各種迅速検査(インフルエンザウイルス、ノロウイルス 等)
- 細菌培養検査
- 皮膚鏡検検査(真菌、疥癬)
- 聴力検査
主な診療内容
生活習慣病
生活習慣病とは、偏った食生活や運動不足、ストレス、喫煙など、毎日の好ましくない生活習慣の積み重ねによって引き起こされる病気の総称です。
代表的なものに、高血圧、糖尿病、脂質異常症があります。
1)高血圧
血圧とは、血液が血管の中を流れる時に血管の壁にかかる圧力のことをいいます。
高血圧の状態を放置すると、血管に負担がかかり血管はしなやかさを失って硬くなり、動脈硬化が起こる原因になります。
動脈硬化が進むと、脳や心臓などで必要としている血液が十分に届かなくなります。さらに進むと、血液が流れなくなってしまいます。これが、脳の血管で起こると脳梗塞になり、心臓の血管で起こると心筋梗塞になります。普段は血圧が高くても何の症状もありませんが、ある日突然、脳梗塞や心筋梗塞などの生命に関わる病気を引き起こす可能性があります。このため、高血圧の治療が必要です。
一方、高血圧の治療をすれば、脳梗塞や心筋梗塞などの発症を予防できる可能性があります。
2)糖尿病
糖尿病は、血液中のブドウ糖の濃度が高い状態、すなわち高血糖状態が続く病気です。
最初のうちは、高血糖が続いても症状はほとんどありません。しかし、高血糖状態が続くと、のどが渇く、疲れやすい、尿の回数が多いなどの症状が現れてきます。更に高血糖状態が続くと、全身の血管や神経が影響を受けてさまざまな合併症が生じてきます。
糖尿病には、3大合併症と呼ばれる目の病気(網膜症)、腎臓の病気(腎症)、手足の神経障害(神経症)があります。これらの合併症は、失明、透析が必要な腎不全、足が腐って切断しなければならなくなる壊疽を生じる原因になります。
また、糖尿病も動脈硬化が起こる原因になり、ある日突然、脳梗塞や心筋梗塞などの生命に関わる病気を引き起こす可能性があります。このため、糖尿病と診断された時には、何の症状を感じなくても、さまざまな合併症を防ぐために、糖尿病の治療が必要です。
一方、糖尿病の治療をすれば、これらの発症を予防できる可能性があります。
3)脂質異常症
脂質異常症とは、血液中に溶けている悪玉のLDLコレステロールが多い、善玉のHDLコレステロールが少ない、中性脂肪が多いといった、血液中の脂質の値が異常な状態をいいます。
普段は、脂質異常があっても何の症状もありません。しかし、脂質異常症も放置すると、動脈硬化が起こる原因になります。このため、ある日突然、脳梗塞や心筋梗塞などの生命に関わる病気を引き起こす可能性があります。このため、脂質異常症の治療が必要です。
一方、脂質異常症の治療をすれば、脳梗塞や心筋梗塞などの発症を予防できる可能性があります。
循環器疾患
高血圧、狭心症、慢性心不全、不整脈など循環器疾患の外来診療を行っております。
循環器疾患とは、血液の循環に関係する心臓、大動脈、肺血管、四肢の動静脈などの病気を指します。
胸が苦しくなる、息苦しくなる、動悸がする、歩くと足が痛くなるなどは循環器疾患である可能性があり、受診されることをお勧めします。
消化器疾患
逆流性食道炎、胃炎、胃潰瘍、腸炎、便秘症など消化器疾患の外来診療を行っております。
消化器疾患とは、胃や腸などの消化管、肝臓、胆道(胆嚢、胆管)、膵臓などの病気を指します。
お腹が痛い、食欲がないなどの症状や、便が黒い、便に血が混じる、体が黄色いなどといったことがみられた場合には消化器疾患である可能性があり、受診されることをお勧めします。
呼吸器疾患
気管支喘息、肺気腫などの慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支炎、肺炎など呼吸器疾患の外来診療を行っております。
呼吸器疾患とは、呼吸に関係する肺、気管支などの病気を指します。
咳が出る、痰が出る、血痰が出る、息切れがする、息苦しい、息をするとゼーゼー・ヒューヒューと音がするなどは、呼吸器疾患である可能性があり、受診されることをお勧めします。
紹介先病院
- 済生会富山病院
- 富山県立中央病院
- 富山赤十字病院
- 富山大学附属病院
- 厚生連滑川病院
- 富山市民病院
- かみいち総合病院
- 金沢医科大学病院
- ほか
紹介元病院
- 済生会富山病院
- 富山県立中央病院
- 富山赤十字病院
- 富山大学附属病院
- 厚生連滑川病院
- 富山市民病院
- かみいち総合病院
- 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
- アルペンリハビリテーション病院
- 糸魚川総合病院
- 富山協立病院
- 金沢医科大学病院
- ほか