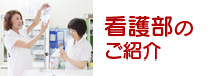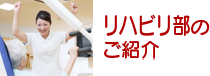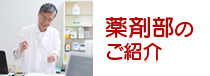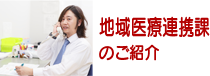理事長のご挨拶
- 医療法人社団尽誠会 理事長
野村病院グループCEO
野村祐介
ご挨拶
―変化の時代に、慢性期医療の未来を見据えて―
野村病院のウェブサイトをご覧いただき、ありがとうございます。
私たちは、かつての「昔ながらの病院」から、着実に生まれ変わってきました。変化する社会・医療に応えるため、組織・体制・理念を見直し、未来を見据えた病院づくりに取り組んでいます。
当院は、昭和42年(1967年)10月1日に開院し、先々代の野村幸男および先代の野村正幸とともに、慢性期以降の患者・利用者の人生を支える医療を大切にしながら、外来および入院診療に取り組んでまいりました。
現在は、その想いを病院理念として受け継ぎながら、医療必要度の高い方の受け入れに対応する慢性期病院として、地域の医療・介護ニーズにお応えしています。
1)理事長である私について ―急性期と慢性期を経験して―
経歴と医師としての経験
私は医師として、循環器内科・消化器内科の領域で診療経験を積み、20年以上にわたり、大学病院や地域基幹病院などの急性期病院で診療に携わってまいりました。
野村病院の継承と経営への関与
熊谷総合病院において診療を継続しながら、先々代および先代の急逝により、野村病院を引き継ぐこととなりました。以後は10年以上にわたり、熊谷総合病院にて勤務医として診療に専念する一方、野村病院では診療に加え、病院の経営にも関与し、両面からの医療提供体制の確立に尽力いたしました。
急性期・回復期・慢性期・介護の現場経験
熊谷総合病院と野村病院の両院に勤務している期間には、救急診療や急性期病棟での診療を通じた「急性期医療」、地域包括ケア病棟および回復期リハビリテーション病棟での「回復期医療」、療養病棟における「慢性期医療」、さらに介護医療院を通じた「介護」分野と、幅広い領域に携わる機会を得ました。
こうした現場経験を通じて、持続可能な医療・介護サービスの実現に必要な課題や仕組みを、実感をもって学んできました。
経営危機の経験と組織運営の学び
熊谷総合病院では、経営母体であった埼玉県厚生連の破産、そしてM&Aによる経営移行といった貴重な経験にも直面しました。この過程で、組織の柔軟な対応力や、地域ニーズに応じた医療提供体制の重要性を深く認識することができました。診療面では、消化器内視鏡医として、常に患者様の苦痛軽減と安全な検査・治療を心がけるとともに、患者様やご家族の生活に寄り添う医療の実現に努めてまいりました。
野村病院での専念と地域医療への貢献
こうした中で、より多くの患者様を支えられる体制づくりに貢献すべく、野村病院での業務に注力する必要性を強く感じるようになりました。
そして令和6年(2024年)の「トリプル改定(診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定)」を一つの契機とし、現在は野村病院の理事長職に専念し、地域に根ざした医療・介護体制の強化に取り組んでおります。
2)VUCA時代における病院の歩み ―3ステップによる病院改革―
病院改革の開始
私は平成24年(2012年)に野村病院の理事長に就任いたしました。当時、病院は経営・組織体制・サービス面などで多くの課題を抱えており、理想とする医療・介護体制には至っていない状況でした。そこで、段階的に組織改革に取り組む必要があると考え、「3ステップによる病院改革」を計画的に進めてまいりました。
・第1ステップ(2012年~):平均的な病院へ
まずは医療機能や体制を再構築し、基本的な医療提供体制を整えることで、地域の皆様に信頼される「平均的な病院」を目指しました。
・第2ステップ(2016年~):生き残る病院へ
慢性期医療を担う病院としての役割を再認識し、療養病棟や介護医療院を通じて安定的な運営と機能強化を図ってきました。当時は、地域に必要とされる存在であり続けるため、時代の変化を見据えながら「慢性期病院として生き残る病院」を目指す意志のもとで取り組みを進めておりました。
・第3ステップ(2021年~):選ばれる病院へ
「地域から、そして医療従事者から選ばれる病院」を目指し、多職種が連携するチーム医療や働きやすい職場づくりに取り組んでいます。
VUCA時代への対応
昨今、医療や介護を取り巻く環境は、変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)を伴う「VUCA時代」と言われています。
こうした社会環境に対応するため、当院では急性期医療で培ったノウハウも取り入れながら、慢性期医療の現場でも質の高い医療・介護を提供できるよう努力しています。
SDGsとESG経営の推進
富山県SDGs宣言のもと、当院は「すべての人に健康と福祉を」「住み続けられるまちづくりを」「人や国の不平等をなくそう」という3つの目標を掲げています。
これらの実現を図るため、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)に配慮した ESG経営 にも積極的に取り組んでいます。
持続可能な医療・介護サービスへ
今後も持続可能な医療・介護サービスを地域に提供していけるよう、継続的な改革と環境適応に努めてまいります。
3)地域とともに歩む病院づくり ―時代のニーズに応える医療提供体制を目指して―
SDGsの理念と地域医療への取り組み
地域から選ばれる病院を目指し、当院では「すべての人に健康と福祉を」というSDGsの目標を掲げ、地域ニーズに即した医療提供体制の整備に取り組んでおります。
完全個室化による療養環境の整備
平成17年(2005年)には、病床の全室を室料差額なしの完全個室化とし、プライバシー保護と感染対策の両立を図った療養環境を整備しました。
高度な慢性期医療ニーズへの対応
当院では、人工呼吸器や気管切開により医療的管理が必要な患者様の受け入れに対応しております。また、医療機関との連携のもと、他県からのご紹介をいただくケースもございます。
安全性に配慮した栄養管理の導入
超高齢社会の進行に伴い、経口摂取や経腸栄養が難しい患者様が増えている現状に対し、中心静脈栄養(TPN)が必要な場合もあります。当院では、中心静脈カテーテルに代わる方法として、感染対策と穿刺時の安全性に配慮した末梢挿入型中心静脈カテーテル(PICC)を平成29年(2017年)より導入し、必要に応じて超音波ガイド下穿刺法を併用しています。これにより、より安全性に配慮した治療の選択肢を提供できるよう努めております。
摂食嚥下支援と多職種連携
摂食嚥下サポートチーム(SST)によるカンファレンスや嚥下内視鏡検査(VE)を導入し、摂食嚥下機能が低下した患者様に対して嚥下機能評価や摂食機能療法などの支援も行っております。これらの取り組みは、医師・看護師・リハビリスタッフなどが協働する、多職種連携のチーム医療体制のもとで実施しています。
生活機能の維持・向上への支援
患者様に対しては、リハビリテーションや入浴支援、排尿自立支援チームの活動など、生活機能の維持・向上に向けた支援にも取り組んでおります。医療的ケアとともに、尊厳を大切にした生活の質の確保を目指しています。
医療と介護の一体的な体制整備
当院グループでは、医療だけでなく介護の分野においても、地域ニーズに応える体制整備を進めています。その一環として、介護医療院・居宅介護支援事業所・訪問介護ステーションを運営しています。
災害対応とBCPの策定
「住み続けられるまちづくりを」という理念のもと、大規模災害等に備えたBCP(事業継続計画)を策定し、万が一の際にもサービス提供が継続できる体制の構築に取り組んでおります。
4)多様な人材が活躍できる職場づくり ―働きやすさを追求する取り組み―
医療従事者から選ばれる病院を目指し、当院では、「人や国の不平等をなくそう」というSDGsの理念を踏まえ、さまざまな背景をもつ医療従事者が安心して働ける職場環境の整備に努めています。
ウェルビーイングの実現を目指して
持続可能な医療・介護の提供体制を支えるため、「残業ゼロ」や「あらゆるハラスメントを許さない職場づくり」をキーワードに、ウェルビーイング経営を推進しています。働きやすい職場環境には業務効率も重要であるとの考えから、以下のような業務支援機器等を導入しています。
・平成30年(2018年):「SOMATOM go」マルチスライスCT導入(タブレット操作に対応)
・令和2年(2020年):生体情報モニター「WEP-1200」導入(医療必要度の高まりに対応)
・令和2年(2020年):とろみ自動調理サーバー導入(職員負担軽減・安全な食事提供を期待)
・令和3年(2021年):見守り支援システム「眠りSCAN」を介護医療院全100室に導入(睡眠状態のリアルタイム把握)
・令和5年(2023年)9月:排尿予測支援機器「D free」導入(排泄ケアの質向上を期待)
・令和5年(2023年)9月:認知症コミュニケーションロボット「だいちゃん」導入(周辺症状軽減、介護負担軽減を期待)
・令和7年(2025年)3月:インカム導入(職員連携・情報共有強化)
医師の働き方改革とチーム医療体制
医師の勤務体制については、完全主治医制ではなく、複数主治医制および当直医制を採用し、平日日中は複数医師による対応、夜間・休日は宿日直許可を受けた当直医が対応する体制を整えています。医療の質と医師の負担軽減の両立を図るものです。
また、事務職を含む全職員の業務効率化を目的に、紙媒体からデジタル化への移行も進めており、チームの一員としての役割意識と働きやすさの向上を図っています。
働く人を支える人事制度とライフステージ支援
令和4年度(2022年度)には、新たな人事評価制度を導入し、スタッフのモチベーション向上に向けた仕組みづくりを行いました。さらに、60歳から65歳へ定年年齢の延長と継続雇用制度により、シニアスタッフの活躍推進にも取り組んでいます。
スタッフ一人ひとりの多様性を尊重する文化が根づいており、たとえばウィンタースポーツの趣味と両立する看護師の夏季限定勤務など、多様な働き方にも柔軟に対応しています。特定看護師(PICCの挿入など)や、認定看護師・専門看護師・診療看護師(NP)など、専門性を持つ看護職の受け入れ体制も整備しています。
また、子育てと仕事の両立支援にも注力しており、厚生労働省が推進する「イクメンプロジェクト」に賛同。男性の育児休業取得実績があり、「イクメン企業宣言」および「イクボス宣言」を令和5年(2023年)4月に行いました。
当院の職場環境や組織運営における取り組みが評価され、株式会社JobRainbowが主催する「D&I AWARD 2023」において「アドバンス」に、「D&I
AWARD 2024」において「ベストワークプレイス」に認定されました。
「DEIB」の推進へ ―働く人が誇れる職場へ―
令和6年(2024年)からは、これまでのダイバーシティ&インクルージョン(D&I)に加え、エクイティ(公正性)の視点も取り入れた「ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)」を推進し、さらにビロンギング(帰属意識)を重視した「DEIB」の実現を目指しています。
「この病院で働いていてよかった」「働き続けたい」と思える職場づくりを進め、誰もが自分らしく、やりがいをもって活躍できる環境整備に取り組んでまいります。
5)デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進と次世代に向けた病院づくり
社会変化と病院のレジリエンス
当院はこれまで、多くの社会的変化や医療環境の課題に直面しながらも、柔軟に対応を重ねてまいりました。そうした過程で、病院としてのレジリエンス(回復力)を高めることができたと考えています。
今後の課題と必要な対応
今後は、新興感染症・再興感染症などの感染症対策をはじめ、少子高齢化や生産年齢人口の減少といった社会的変化にも対応し続ける必要があります。これらの課題に対し、これまで培ってきた対応力を生かしながら、より柔軟かつ持続可能な体制づくりを進めてまいります。
当院では、柔軟で持続可能な医療・介護体制を構築するための取り組みやDXによる体制強化を通じて、「医療・介護における新たな取り組み」と「職場環境における新たな挑戦」を両立させ、将来を見据えた病院・施設の在り方の検討と価値の創出を進めたいと考えています。
DXによる体制強化
こうした取り組みを支える重要な基盤の一つが、デジタルトランスフォーメーション(DX)です。
当院ではこれまで、ICT・ロボット・医療介護デバイスの導入など、医療・介護現場のデジタル化を積極的に進めてまいりました。
デジタル化の成果と展望
DXの推進により、従来の業務効率向上や医療安全対策に加え、今後の医療・介護の変化にも対応可能な環境整備を図っています。
次の60年に向けて
令和9年(2027年)、私たちは開院60周年を迎えます。
これからも、「地域から、そして医療従事者から選ばれる病院」を目指し、次の60年に向けて、その時代に合った病院づくり・施設づくりに取り組んでまいります。
今後とも、皆様のご理解とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
略歴
| 平成13年(2001年) | 金沢医科大学 医学部卒業 金沢医科大学 循環器内科入局 |
| 平成16年(2004年) | 先端医学薬学研究センター 臨床研究開発部研究員 |
| 平成17年(2005年) | 石川医療技術専門学校 循環器内科非常勤講師 |
| 平成18年(2006年) | 金沢医科大学大学院 内科学Ⅰ修了(医学博士) 金沢医科大学 循環器内科 医員 |
| 平成19年(2007年) | 金沢医科大学 循環器内科 助教 金沢医科大学附属看護専門学校 循環器内科非常勤講師 |
| 平成21年(2009年) | JA長野厚生連 佐久総合病院 胃腸科 |
| 平成24年(2012年) | JA埼玉県厚生連 熊谷総合病院 消化器内科 医療法人社団尽誠会 理事長就任 |
| 平成25年(2013年) | 富山大学附属病院 第三内科 医員 富山県済生会富山病院 消化器内科 |
| 平成26年(2014年) | JA埼玉県厚生連 熊谷総合病院 消化器内科 |
| 平成28年(2016年) | 医療法人 熊谷総合病院 消化器内科 |
| 令和 3年 (2021年) | 医療法人 熊谷総合病院 副医局長 |
| 令和 4年 (2022年) | 医療法人 熊谷総合病院 医局長 |
| 令和 6年 (2024年) | 医療法人社団尽誠会 野村病院 医療法人 熊谷総合病院 内視鏡センター非常勤医師 |
学会認定専門医等
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
日本循環器学会認定循環器専門医
日本消化器病学会認定消化器病専門医
日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医
日本消化管学会認定胃腸科認定医・専門医
日本消化管学会便通マネージメントドクター
日本老年医学会認定老年科専門医・指導医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
日本スポーツ協会公認スポーツドクター
日本心臓リハビリテーション学会認定心臓リハビリテーション指導士
難病指定医
認知症サポート医
日本認知症学会・日本老年精神医学会 「アルツハイマー病の病態、診断、抗Aβ抗体薬の投与対象患者及び治療に関する研修」 修了
日本老年医学会認定高齢者医療研修会(総合機能評価加算に係る研修) 修了
日本栄養治療学会TNT(Total Nutrition Therapy)研修会 修了
嚥下機能評価研修会(PDN VEセミナー) 修了
下部尿路機能障害の治療とケア研修会(排尿自立支援加算・外来排尿自立指導料該当研修) 修了
がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会 修了
フェントス®テープ適正使用e-learning 修了
医師の臨床研修に係る指導医講習会 修了
厚生労働省指定オンライン診療研修 修了
富山県慢性期医療協会副会長
富山市介護認定審査会委員
メディア掲載・講演実績
2026年
1月|医療情報誌『医心』
2026年1月号「ISHIN column」において「奇跡的に生まれ変わった野村病院 〜危機から脱却し慢性期医療の新たなモデルを築く軌跡〜」vol.3「慢性期病院として生き残るための挑戦(後編)」として野村祐介理事長の取り組みが掲載されました。
1月|最新医療経営『PHASE3』
高齢者医療の課題について、金沢医科大学氷見市民病院 最高経営責任者(CEO)神田享勉氏との対談形式で、野村祐介理事長のインタビュー記事が掲載されました。
2025年
11月|医療情報誌『医心』
2025年11月号「ISHIN column」において「奇跡的に生まれ変わった野村病院 〜危機から脱却し慢性期医療の新たなモデルを築く軌跡〜」vol.2「慢性期病院として生き残るための挑戦(前編)」として野村祐介理事長の取り組みが掲載されました。
11月|専門誌『病院経営羅針盤』
2025年11月15日号 特集「機能転換の決断と戦略設計」において、野村祐介理事長の寄稿記事「制度変化をチャンスに変えた病院経営の決断 ~慢性期治療病院への挑戦と組織改革~」が掲載されました。
10月|KNBラジオ「とれたてワイド朝生!」
「健康と暮らしのヒント・からだ想いラジオ」コーナーにて、野村祐介理事長が健康診断の大切さについて語りました。
9月|医療情報誌『医心』
2025年9月号「ISHIN column」において、「奇跡的に生まれ変わった野村病院 〜危機から脱却し慢性期医療の新たなモデルを築く軌跡〜」vol.1「危機に直面した野村病院と基盤づくりの第一歩」が掲載され、野村祐介理事長の取り組みが紹介されました。
9月|月刊誌『病院』
2025年9月号に「事例と財務から読み解く 地域に根差した病院の経営 医療法人社団尽誠会野村病院──危機的な状況を乗り越え『地域から、そして医療従事者から選ばれる病院』への変革」が掲載され、野村祐介理事長の取り組みが紹介されました。
7月12日|北日本新聞
看護師の特定行為研修制度に関する記事において、野村祐介理事長の視点が紹介されました。
5月22日|チューリップテレビ「ニュース6」
医師の働き方や美容医療に関する特集において、野村祐介理事長のコメントが放送されました。
4月|中小企業応援サイト
病院運営に関する取り組みについて、野村祐介理事長のコメントが紹介されました。
4月|DIVERSITY GUEST TALK(Vol.1〜5)
野村祐介理事長がYouTube番組に出演し、以下のテーマで当院の取り組みを紹介しました。
- Vol.1:DE&I推進活動
- Vol.2:多様な人材が活躍できる職場づくり
- Vol.3:広報を活用した慢性期医療のイメージ刷新
- Vol.4:組織における多様性の推進
- Vol.5:多様な視点を取り入れた経営改革
3月|KNB WEB
インカム導入とICT化推進について、野村祐介理事長の見解とともに報道されました。
2月7日|北日本新聞「風車」コーナー
「ウェルビーイング自販機」設置に関する取り組みについて、野村祐介理事長の見解が紹介されました。
1月27日|KNB
WEB
健康増進と災害対策を兼ねた自動販売機の導入について、野村祐介理事長の方針が掲載されました。
1月15日|チューリップテレビ「ニュース6」
ペイシェント・ハラスメント対応事例として、野村祐介理事長の取り組みが紹介されました。
2024年
11月|第8回 日本在宅救急医学会学術集会(福井) ランチョンセミナー2
シームレスな栄養管理について野村祐介理事長が講演しました。
座長:中村謙介 先生(横浜市立大学附属病院 集中治療部 准教授)
11月|ナリコマホールディングス Webサイト「SPECIAL事例インタビュー」
慢性期医療の展望について、野村祐介理事長のインタビューが掲載されました。
11月|『最新医療経営 PHASE3』
野村祐介理事長の経営哲学と組織改革の事例が取り上げられました。
9月16日|北日本新聞
看護師の睡眠改善に関する研究について、野村祐介理事長の視点が紹介されました。
8月|CBnews
「広報で慢性期医療を変える【病院広報アワード】固定概念からの脱却」において、病院広報アワード2024 経営者部門 優秀賞を受賞した野村祐介理事長の取材記事が掲載されました。
7月10日|チューリップテレビ「ニュース6」
認知症支援におけるセラピー犬活用について、野村祐介理事長の考えが紹介されました。
5月|医療ウェブメディア「m3.com」掲載(全3回)
- Vol.1:オンライン診療活用について野村祐介理事長が紹介されました。
- Vol.2:病院のイメージ転換について野村祐介理事長の方針が紹介されました。
- Vol.3:働き方改革における成果について、野村祐介理事長の見解が紹介されました。
4月|医療情報誌『医心』
慢性期医療の刷新に向けた活動について、野村祐介理事長の取り組みが紹介されました。
4月|DFree社 Webサイト
排泄予測機器導入事例として、野村祐介理事長のコメントが紹介されました。
3月|摂食嚥下×栄養 セミナー&試食会(富山)
多職種連携における栄養管理とリハビリテーションについて、野村祐介理事長と摂食嚥下サポートチームが講演しました。
3月|ダイドードリンコ Webサイト
「女性ヘルスケア応援自販機」設置に関する背景を野村祐介理事長が説明しました。
3月11日|KNB
WEB
働きやすさを重視した病院運営について、野村祐介理事長のコメントが掲載されました。
3月|ネスレ日本株式会社 特別セミナー
「働き方改革と病院改革の実践」をテーマに、野村祐介理事長が講演しました。
2月|Otsuka Nutrition Webinar
脂肪乳剤入りアミノ酸末梢輸液を活用したリハビリ・口腔・栄養の一体的取組の実践について、野村祐介理事長が講演しました。
座長:佐藤弘 先生(埼玉医科大学国際医療センター 上部消化管外科 教授)
2月|カーディナルヘルス Webサイト
チーム医療とタスクシフト推進について、野村祐介理事長の視点から紹介されました。
2月23日|北日本新聞
自販機での生理用品販売について、野村祐介理事長の方針が取り上げられました。
2月19日|食品新聞
社会貢献型自販機導入における野村祐介理事長の考えが紹介されました。
2月9日|日本食糧新聞
社会貢献型自販機導入に関して、野村祐介理事長の方針が取り上げられました。
1月25日|NHK「おはよう日本」
津波避難への取り組みに関し、野村病院の見解が報道されました。
1月23日|NHK「ニュース富山人」
津波避難対策の課題と現場の取り組みについて、野村病院の見解が報道されました。
1月15日|北日本新聞
能登半島地震時の津波避難対応として、野村病院の考えが紹介されました。
2023年
12月24日|北日本新聞「富山市SDGs MONTHLY NEWS」
食品ロス削減や職場環境改善に関する取り組みについて、野村祐介理事長の方針が紹介されました。
12月15日|北日本新聞
健診後オンライン診療導入について、野村祐介理事長の方針が紹介されました。
12月1日|北日本新聞「風車」
セラピー犬との交流イベントにおいて、野村祐介理事長が紹介されました。
11月16日|富山新聞
オンライン診療導入の取り組みについて、野村祐介理事長の戦略が掲載されました。
10月27日|日本経済新聞
企業健診再検査を支援する施策として、野村祐介理事長の取り組みが紹介されました。
10月27日|北日本新聞
介護医療院のノンアルサービスに関する野村祐介理事長の方針が報道されました。
10月9日|KNBラジオ「とれたてワイド朝生!」
「健康経営」コーナーにて、野村祐介理事長が出演しました。
10月|書籍『明日の高齢者医療を拓く 2024年版』
野村祐介理事長および野村病院の慢性期医療に関する取り組みが紹介されました。
10月3日|北日本新聞
ICT機器活用による職員負担軽減について、野村祐介理事長の見解が紹介されました。
9月|ナリコマグループ Webサイト
給食体制の見直しとスタッフの活用について、野村祐介理事長の方針が掲載されました。
6月|熊谷病診連携セミナー(埼玉)
野村祐介理事長が「慢性期医療における摂食嚥下の実際」について講演しました。
座長:斎藤雅彦 先生(熊谷総合病院 副院長・内科診療部長・総合健診センター長)
5月|九州医事新報
無人販売機によるフードロス削減への取り組みとして、野村病院の取り組みが紹介されました。
4月|無印良品 Webサイト
訪問販売との連携について、野村祐介理事長のコメントが掲載されました。
4月20日|北日本新聞
食品ロス削減に向けた施策として、野村祐介理事長の取り組みが報道されました。
4月|『ヘルスケア・レストラン』
介護医療院における排便支援の体制について、野村祐介理事長の姿勢が紹介されました。
2月17日|富山新聞
特別休暇制度の導入背景と効果について、野村祐介理事長の見解が紹介されました。
2月|デロイトトーマツ Webサイト
医療機能強化と採用施策の事例として、野村祐介理事長の取り組みが紹介されました。
1月13日|北日本新聞
地域交流としてのキッチンカー運用について、野村祐介理事長が紹介されました。
2022年
12月|摂食嚥下サポートセミナー(金沢)
野村祐介理事長が「摂食嚥下サポートチームの立ち上げと慢性期医療における実際」について講演しました。
座長:辻裕之 先生(金沢医科大学病院 摂食・嚥下センター長/頭頸部外科学 名誉教授)
10月|『けあ・ふる』vol.113
見守り支援と多職種連携の取り組みについて、野村祐介理事長の活動が紹介されました。
9月|テルモ株式会社パンフレット
中心静脈栄養施行患者に対する摂食・嚥下機能回復に向けた取り組みが紹介されました。
2021年
3・4月号|『栄養経営エキスパート』
嚥下調整食の栄養価向上に関する工夫として、野村祐介理事長が紹介されました。
3月8日|チューリップテレビ「ニュース6」
「保険制度の隙間を埋めるボランティアナース」に関して、野村祐介理事長のコメントが放送されました。
3月|光電シグナル
機器導入に対する利用価値・評価について、野村祐介理事長のコメントが掲載されました。
2020年
10月|『月刊新医療』
慢性期病院におけるCT活用の実践について、野村祐介理事長の方針が掲載されました。
1月10日|大塚製薬工場主催 座談会
中心静脈栄養に関する意見交換にて、野村祐介理事長が司会を務めました。
2019年
11月|富山地区医療マネジメントセミナー
野村祐介理事長が座長を務め、医療経営に関する講演が行われました。
演者:楠山龍 先生(株式会社ヒューマンプランニング 取締役統括マネージャー)
3月|大塚薬報
慢性期病院の役割と急性期病院との連携について、野村祐介理事長の取り組みが紹介されました。