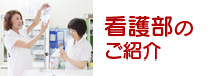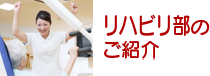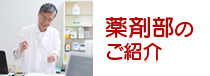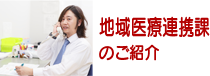嚥下内視鏡検査(VE)による嚥下機能評価と手順 ~多職種連携によるチーム医療を推進する~
2025.06.12
1) 超細径電子スコープによる嚥下内視鏡検査
医療法人社団尽誠会 野村病院では、飲み込みにくさ(嚥下障害)を調べるために嚥下内視鏡検査(VE:videoendoscopic examination of swallowing)を行っています。
嚥下内視鏡はペンタックス社の超細径電子スコープを導入しており、先端外径φ2.4mmの細いタイプの内視鏡です。

2) 嚥下内視鏡検査による嚥下機能評価と手順 ~摂食嚥下サポートチームによる多職種連携とチーム医療~
嚥下内視鏡検査の手順は、先端外径φ2.4mmという細い内視鏡を鼻(鼻腔)から挿入し観察します。まずは、のど(咽頭)の唾液のたまり具合を評価します。
続いて、少量の着色したとろみありの水やとろみなしの水、ゼリー、ペースト食やお粥などの実際の食事を飲み込んでもらいます。
飲みこみが起こるタイミング、飲み込んだ後の残留の程度、気管への流入(誤嚥の有無)、噛む状態(咀嚼状態)、咳反射の起こりやすさ等を観察することにより、嚥下の状態を評価(兵頭スコア)することができます。
この評価結果により、今後の嚥下訓練の可否や程度、食事形態や食事時の姿勢等について方針を摂食嚥下サポートチームのカンファレンスにて決定していきます。

3) 嚥下内視鏡検査の実際と嚥下内視鏡検査における感染対策
嚥下内視鏡検査は、日本消化器内視鏡学会認定消化器内視鏡専門医である野村 祐介医師および、金沢医科大学病院 摂食・嚥下センター 助教の川上 理医師が担当しています。
また、外来診察室で行っていますが、病室(ベッドサイド)でも検査を行うことができます。
なお、当院では内視鏡を介する感染事故を防止するため、感染対策も重要視しています。
当院では内視鏡の自動洗浄機を導入し、検査ごとに自動洗浄機にて完全に消毒してから次の患者様に使用しております。